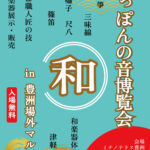『虚無僧』イメージの尺八って、海外じゃ
日本とは違った印象で、大人気なんです。
知らんかった・・。
尺八ってオーケストラ楽器だっけ?

(イメージ)
2024年7月12日に、仕事でオフィスで打ち合わせが
終わり帰宅したら一件のLINEが入って、
そのまま、豊洲までトンボ帰り。
日本尺八演奏家ネットワーク通称、JSPNという
団体があって、流派を超えて世界の尺八の演奏家と
交流を深めている組織の公演だというので行ってきました。
初めて「尺八」の公演を生で観たんですが、
津軽三味線と民謡の公演しか知らない自分にとって、
刺激的でしたね。クラッシックオーケストラの
公演を観ているようで、多分、多くの人の尺八に対する
イメージとはだいぶ違うんじゃないかと思う。
予想より近代的な印象でした。
津軽三味線界隈より、尺八はグローバル化していた!

そして、なんといっても和楽器界隈にしては
『グローバル化』がとても進んでいる。
なんで、もっと公に注目されないのか、不思議なくらい。
公演の後半は、「世界の尺八演奏家」と題して、
演奏じゃなくて世界の奏者の映像を見せられるのも新しい。
このアプローチは、イマっぽくて、オシャレだし、
アイスブレイク的な効果もあって、良いな、と思った。
因みに、民謡界隈とかの演奏会や公演って、
6時間とか当たり前で、初めて行った時は、ぶったまげた。
人生の先輩方、まだまだ、元気いっぱいです・・・。
(3~4千円のチケット代のコスパとしては最高だと思う)
世界の尺八マインドは、オシャレで本質的だった件
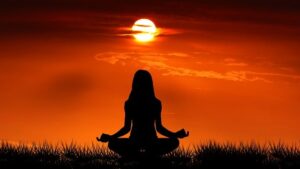
(イメージ)
アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、台湾・・と
各国の尺八の奏者が出てくるんだけど物凄く、考え方が哲学的。
ソウルサーファーと同じマインドで尺八をしているのが
理解できた。つまり、テクニックや知識も大事かもしれないけど、
それよりも「自分と繋がること」「世界と繋がること」
もっと言えば「宇宙と繋がること」その次に古典曲や、
テクニック的な話になってくる、そんな印象。
「スタイル」が日本よりも虚無僧的な海外勢。
尺八に限らず、なんでもそうだけど、日本って、
演奏曲やテクニック、道具なんかに意識を向けがちだけど、
海外の方って「本質」から入るからカッコいい。
その人の「スタイル」が滲み出てる。
ある意味、本当に「虚無僧」的なスタイル。
カッコいいから、海外で流行ったものに日本人は飛びつく。
業界を活性化、継承していきたいなら、
その日本人の性質(メリット?)をおおいに活用するべきだと思う。

(イメージ)
最近は日本人と同じく、世界でも若い層のアプローチは、
「楽器」としてや、演奏方法寄りに傾いてるらしい・・・。
でも、その辺はサーフィンも同じ。最初はカッコから入るけど、
どんどん、精神性を求めるようになればシメたものww
いずれにしても、何で尺八は海外でブレイクしたのか?
「カルチャー」として、根付きつつあるのか?
深掘りすると、日本の伝統芸能発展の参考になるのでは
ないでしょうか。
そんな『邦楽ジャーナル』8月号の内容がこちら↓

P.S.
国会図書館にも所蔵されているのに、
書店では買えないという、マニアックさ・・。
今日も良い1日を!